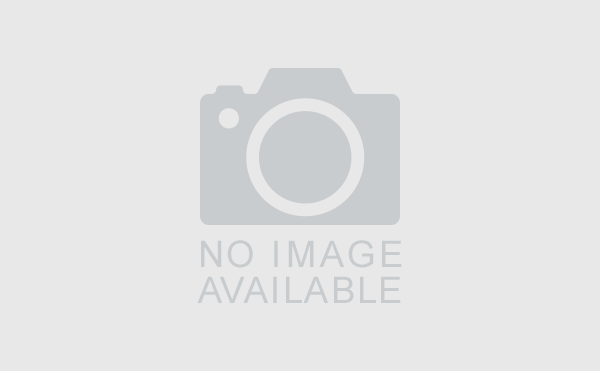国立大病院、稼働率を上げても赤字から脱却できず
国立大学病院長会議(以下、同会議)は今年(2025年)7月、昨年度の決算が、国立大学法人化以降、最大の経常損益となる285億円のマイナスを報告した。働き方改革による人件費の増加や急激な物価高騰と相まって厳しさを増すばかりだ。同会議会長の大鳥精司氏(千葉大学病院長)は昨日(8月20日)、東京都で開いたメディア懇談会で「診療稼働率を上げても赤字から脱却できない」と窮状を訴えた。(関連記事「国立大病院、いまだ赤字213億」「【緊急取材】『研究機能の破綻は不可避』ー国立大病院の経営難で」)
「診療報酬の改定が物価上昇による支出に追い付いていない」
大鳥氏は昨年度の損益速報値に影響した要因などについて総括した。
国立大学病院全体の収益は、新型コロナウイルス流行後から回復を見せ、合計で対前年度比547億円増加した。一方、費用は人件費が303億円、診療経費が436億円それぞれ増加し、これらなどを合わせて対前年度比772億円増となった。そのため、昨年度の経常損益は285億円と深刻な状況となった。赤字が最も深刻だった大学病院では60億円以上にも上っていた。
増収減益に影響した要因として、コロナ関連の補助金交付により見かけ上、黒字だったが交付が打ち切られてしまったこと、働き方改革による人件費の増加、急激な物価高騰が挙げられる。今年は診療報酬の改定がない年であり、今年度も赤字幅はさらに増すと考えられる。
費用負担を見ると、2018年度の医薬品費は2,803億円、診療材料費などは1,744億円だったのが、昨年度はそれぞれ4,065億円、2,239億円に増えていた。2018年度に比べ診療稼働率が上昇した一方で、費用負担が増加。同氏は「診療報酬の改定が物価上昇による支出に追い付いていない」と指摘し、「いくら診療を増やし、稼働率を上げても結局は赤字から脱却できない負のスパイラルに陥っている」と説明した。
大学病院はつぶれかねない
高難度治療にかかる医薬品・診療材料費が高騰しているため、医療機関全体の医療費率が22.1%であるのに対し、大学病院は43.0%と極めて高い。
社会では、診療材料費も保険償還されるのだから経営に影響しないとの誤解がある。しかし、高度先進医療に要するガーゼや手術器具などは病院の持ち出しで、昨年は42大学病院全体で1,010億円計上された。抗がん薬自体は診療報酬になるが、患者の状態が悪く当日投与できなければ、これも病院負担となる。
さらに、臓器移植施行についても臓器移植ネットワークへの支払いや移植周術期に関わる職種の人件費、集中治療室(ICU)管理費などを要し、例えば最も高額な肺移植施行では1件当たり-418万8,529円となり、大学病院としての使命を果たす上で障壁となっているといわざるをえない。
医療の提供に加え教育および研究も行う大学病院の機能を考えると、「診療報酬や補正予算による支援がないと、大学病院はつぶれかねない」と大鳥氏は訴えた。